告訴状・告発状作成サポート
ガルエバー行政書士事務所
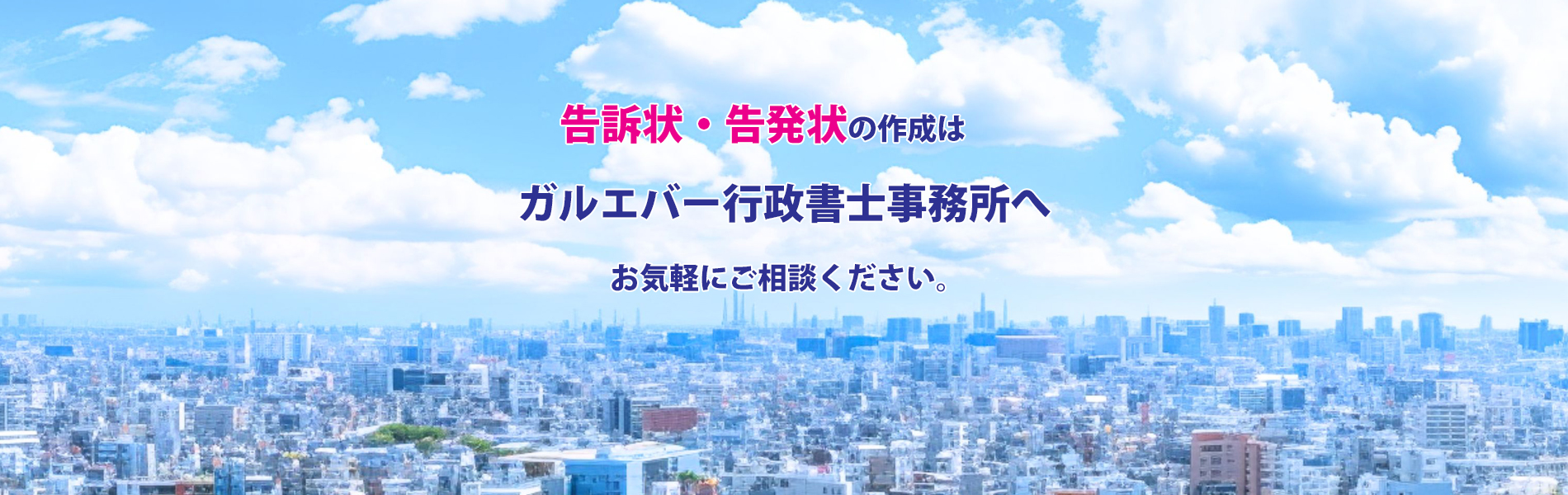
サービス内容
サービス料金
お問い合わせ
Eメール(宛先 info@galever.com)又は下記のお申込みフォームにてお申込みください。
お問い合わせフォーム
ご依頼の流れ
- Step 1. お申込み ・お問い合わせ
(ご依頼者→当事務所) - ・お申込みフォーム、電話(070-9086-6253)、メール(info@galever.com)からお申込み下さい。
- Step 2.ヒアリング
(ご依頼者様 ⇔ 当事務所) - ・現在のご状況をヒアリングして、告訴・告発の可能性を検討します。
- Step 3.原案の作成 ・確認・修正
(当事務所⇔ご依頼者様) - ・当事務所で原案を作成します。
・ご依頼者様に確認していただき、不備があれば修正します。
- Step 4.警察署への提出
(ご依頼者様→警察署) - ・ご依頼者様が警察署へ出向き提出します。
・警察から指導があれば必要に応じ修正します。
よくあるご質問 Q&A
知っておくと安心。 刑事手続きに関する法律用語集
「職務質問」とは、警察官が挙動不審な者を停止させて質問をすることです。警察官が職務質問を行える根拠は、警察官職務執行法(警職法)第2条第1項にあります。
この規定は、警察官が、異常な挙動や犯罪を行ったか、犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者に対して、停止させて質問することができるとしています。
職務質問は犯罪を事前に予防するために認められる権限で、このような警察による犯罪の事前事前予防活動を行政警察活動と呼びます。
一方、犯罪発生後に行われる警察活動を司法警察活動といいます。
「取調べ」とは、被疑者や被疑者以外の第三者から事情を聴いたり、説明を求めることです。
刑事訴訟法第198条1項では「検察官、検察事務官または司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求めこれを取り調べることができる」として、被疑者の取調べについて規定しています。
「捜査」は、警察をはじめとする捜査機関が、犯罪があると考えるときに、犯人と思われる者(被疑者)を特定・発見し、必要な場合にはその身柄を確保するとともに、証拠を収集・保全する、一連の手続きです(法第189条2項参照)。
これは、主として、検察官による起訴・不起訴の決定、および、公判における主張・立証活動に資することを目的としてなされています。
「逮捕」とは、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き一定時間、身柄の拘束を継続することをいいます。 逮捕のおもな目的は、 ① 被疑者の身柄を確保することと、 ② 被疑者による証拠の破壊や関係者に対する脅迫を防止すること にあります。 逮捕には、3つの種類があります。通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕です。 それぞれ逮捕 のための要件や手続が異なりますので、注意が必要です。
検察官は、法務省の機関である検察庁所属の国家公務員です。
犯罪の捜査から、公訴の提起、公判の立合い、裁判の執行まで、刑事手続の全段階にわたって関与します。
とりわけ、公訴の提起に関する判断が、原則として検察官の裁量的判断にかかっているため、刑事事件の処理の上で大きな役割を果たしています。
そして、その職務権限が司法権の行使と密着しているため、通常の行政官と異なり、職務の独自性が認められています。
また、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ(法第191条)、司法警察職員よりも強い捜査権限をもっています。
起訴とは、検察官が裁判所に対し、犯罪事実について審判を求める意思表示で、公訴の提起ともいわれています。 検察官のみが有効に起訴(公訴提起)することができます(起訴独占主義 法第247条)。